だいず加工食品①とうふ
とうふが日本に渡来したのは奈良朝のころで、唐に留学していた僧が帰国して伝えたものだといわれています。昔の高僧などが全く肉食をしないで、極端な粗食でありながら長寿を保ったのは、とうふ類の効果によるところが多かったといわれています。肉食を嫌う寺院では、良質のタンパク源として精進料理の重要な食材となり、とうふをさらに加工した食品も数々生まれてきました。
近年は、欧米でも生活習慣病を予防する食材として積極的に取り入れられているタンパク源です。
とうふ一丁に含まれるタンパク質は、タマゴなら3個分、牛肉なら100グラム分に当たります。しかもタンパク質や脂肪の消化吸収率は95パーセントと吸収されやすいので、胃腸の弱っている人や赤ちゃんの離乳食にも最適です。体内で無駄なく役に立ちます。またダイズのサポニンがコレステロールを分解し、血液の循環をスムーズにしてくれるので、動物性タンパク質が原因になりがちな生活習慣病を予防する効果が大きいのです。
国産ダイズを原料とするとうふなら、リノール酸やビタミンEもたっぷりなので、動脈硬化の防止や老化の防止にも役立ちます。
とうふは種類によってかなり成分が違います。木綿どうふは木綿で漉して作りますのでタンパク質やカルシウムや鉄分が豊富です。成分的には肉の代わりになり、炒めものに向いています。
絹ごしどうふは、漉さないでうわずみもそのまま豆乳全体を固めますので水溶性のカリウムやビタミンB1が豊富です。口当たりがよいので冷や奴や湯どうふにすると美味しくいただけます。冷や奴にかつお節という取り合わせは、不足するアミノ酸を補い合い、トータルで大変良質のタンパク源となります。かつお節のビタミンDは、豆腐のカルシウムの吸収率をかなり高めてくれます。コンブやワカメなどヨウ素の多い食品といっしょに摂ることが多いのは甲状腺の肥大を防ぐ組み合わせで、先人の知恵をしみじみ感じさせられます。
そのかみの
恋女房や新豆腐
日野草城
西野次朗
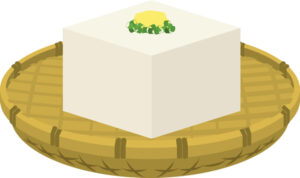
この記事はヨガライフスクールインサッポロ機関紙 「未来」472号(2025年4月5日発行)に掲載された記事です。
 |
著者 |
|
略歴 |
|
