ネギは栄養たっぷりの野菜です
すき焼きや鍋物、そばの薬味など、さまざまな料理に欠かせないのがネギ。
古くから日本人は、ネギを大切に育ててきました。
ネギの原産地はシベリアとされていますが、これを自分の国のものとして、
毎日の料理に欠かすことのできないものに育て上げてきたのは日本人です。
中国では、周代の文献にネギのことを「本白く末青し」とあるそうですが、
今日では、その消費量はごく僅かのようですし、
ヨーロッパでもサラダの香辛料として、少量栽培されている程度です。
わが国では『日本書紀』に「秋葱」と記されていて、
天皇即位の大嘗会には、神饌のひとつとしてお供えされています。
ネギの食用部分は葉ですが、葉には白い部分と緑色の部分があります。
ネギにはいずれもネギ臭と呼ばれる特有の刺激臭があります。
この主成分は含硫化合物で、刻んだり、たたくなどして細胞が壊れると酵素が作用して生じます。
玉ねぎやニンニクなどのにおい成分と共通の物質です。
このにおい成分の含硫化合物には多くの生理作用があります。
含硫化合物のアリシンはビタミンB1と結合すると、吸収率が高く、効果が持続するB1に変化します。
つまり、ネギを豚やレバーなどB1の多い食べ物といっしょに食べると
B1が効率よく利用されることになります。
ビタミンB1の吸収をよくすることはエネルギーの代謝を高めることに繋がりますので、
疲労の回復やスタミナの強化、風邪にネギが良いのはこの作用が関係しています。
また、血栓を防いだり、鎮痛・解熱など、その働きがアスピリンと同じような仕組みなので、
ネギ類は天然アスピリンと呼ばれています。
また、ネギには白血球の増加作用があることが動物実験で確かめられています。
その働きで免疫力が高まり、ガンをはじめ病気に対する抵抗力が増します。
江戸初期の『料理物語』に、「ねぶか(長葱)汁、味噌を濃うしてダシ加え一塩の鯛を入れてよし、
すましにも仕立て候」とありますが、魚の生臭みを消すのにもよく効くことを教えています。
貧厨に葱噛む昼の鼠かな
尾崎紅葉
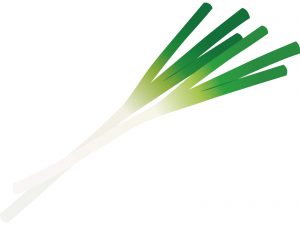
この記事はヨガライフスクールインサッポロ機関紙 「未来」406号(2019年10月5日発行)に掲載された記事です。
 |
著者 |
|
略歴 |
|
