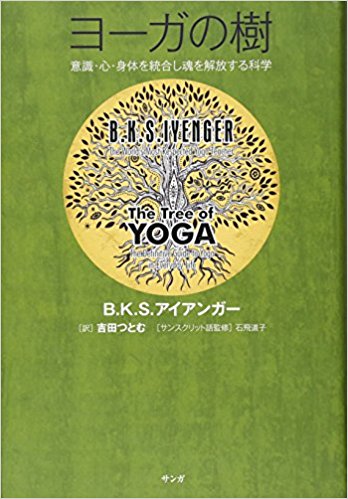so ‘ham ― 私はそれ(tat)である ― Ⅱ
- ヨガ
mahaanaaraayana-upanishad(マハーナーラーヤナ・ウパニシャッド)の冒頭のsvasti paatha(スヴァスティ・パータ、幸運の詩句)から:
om
asato maa sad gamaya
tamaso maa jyotir gamaya
mrityor maa ‘mritam gamaya
om shaantih shaantih shaantih
オーム
非実在(虚偽)から実在(真実)へと私を導き給え
暗闇から光明へと私を導き給え
死から不死へと私を導き給え
オーム、シャーンティ、シャーンティ、シャーンティヒ
bhagavad-giitaa(バガヴァッド・ギーター)、17―23から:
om tat sad iti nirdesho brahmanas tri-vidhah smritah
braahmanaas tena vedaash ca yajnaash ca vihitaah puraa
「オーム(聖音)、タット(それ、真実)、サット(実在、真実、存在すること)はブラフマンを示す三種の語句であると伝えられる。それによってかつてブラーフマナ、ヴェーダ、祭祀が創造された。」
私は生涯の大半をヨーガの中に生きてきて、ヨーガやインド思想、仏教などが古代インドで隆盛し、その後なぜ中・近世を経てほぼ絶滅してしまったのか疑問に思い、またどのように西洋に渡り現代に再生されるようになったのか、その根本原因を知りたいと思ってきました。
パタンジャリが著したヨーガスートラは現代のヨーガの世界でも古典ヨーガとして最も重視されるヨーガ文献の一つで、その時代考証は学者により諸説あり、時代を経て付加や改変されたようです。またその解説も古くから数多く書かれ、西洋諸国や日本でも種々翻訳されてきました。佐保田鶴治氏や中村元氏を始め仏教論者の多くはその中核となる思想は仏教の影響を受けていると論じ、ヴェーダーンタ論者の中にはその逆にサーンキャ学派やヨーガ学派が仏教に影響したとする論者もいます。また第三の説として古代インドには仏教やサーンキャが興る以前に文献には残されていない思想体系の母体があり、そこからその理念がサーンキャやヨーガあるいは仏教にも流れたとする論者もいます。
しかしこれらは些末な説や論に過ぎず、肝心なことはその核となるものが真実に存在するもの(sat)かあるいは思考が作り上げた理念に過ぎないのかということです。それが真実であれば何から何に影響したかということを超えて共有されるべきもので、古代インドにも現代の日本にも時空を超越して共に存在する価値を持つでしょう。古代インドのある時代に流行し時代や社会的背景が変化して消滅するものであればそれは真実性を持たず、単なる思考が作り上げた一理念にすぎないことを示しています。
以前にヨーガスートラのⅣ~Ⅵ:puraana-aayaama(プラーナ・アーヤーマ、プラーナの伸展・拡張)、praty-aahaara(プラティ・アーハーラ、本源に帰ること)、dhaaranaa(ダーラナー、精神性の静止、把持)について触れ、仏教論者たちがそれらを人間の本質的で自然な状態や感情を抑圧し、抑制・制御するabhyaasa(アビヤーサ、修行、常習)として捉え解釈していることを伝えました。
ヨーガを実践もせず内的な理解もない学者たちがヨーガを解釈し論じるとき、その理解は言葉の概念や思考による外面的なものになり、古典ヨーガとしてのヨーガスートラを禁欲や苦行(tapas)を中心論調として解釈することになります。インドではその後ハタヨーガの時代となり奇怪に歪んだものへと逸脱しやがて絶滅します。その根本原因は禁欲や苦行、自然な在り方の抑圧や抑制にあると私は見ています。
ヨーガやヴェーダーンタが欧米を経て現代に再生されたとき、禁欲や苦行のような虚構は脱落しその本質的なものが蘇ったと見られます。「それ」はヨーガや生の「楽しみ」や「喜び」であり、「それ(tat)」を私たちの存在の内奥に見出すことであり、また「それ」を他者や自然と分かち合い共感・共鳴し、交感・合歓することにあると。「それ(tat)」はウパニシャッドでも中心課題として謳われてきたものでもあります。
令和7年4月17日
この記事はヨガライフスクールインサッポロ機関紙 「未来」473号(2025年5月7日発行)に掲載された記事です。